受給者証とは?必要な理由や放課後等デイサービスの申請方法を解説
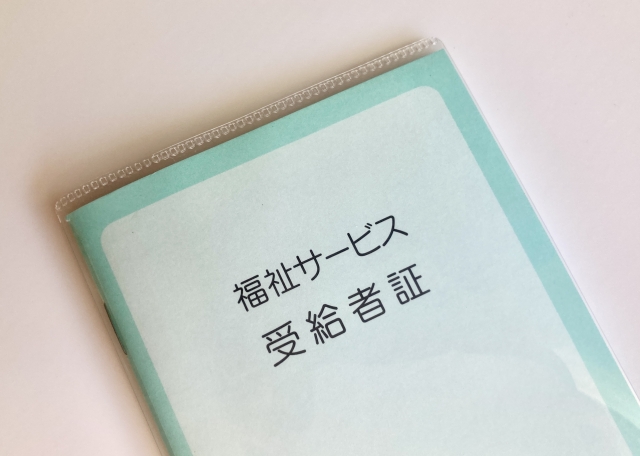
受給者証は、児童発達支援や放課後等デイサービスなど、障がいのある子どもの福祉サービスを利用するために必要です。
本記事では、受給者証の概要や種類、必要な理由を解説します。これから受給者証を申請しようと考えている方は、参考にしてください。
受給者証とは?
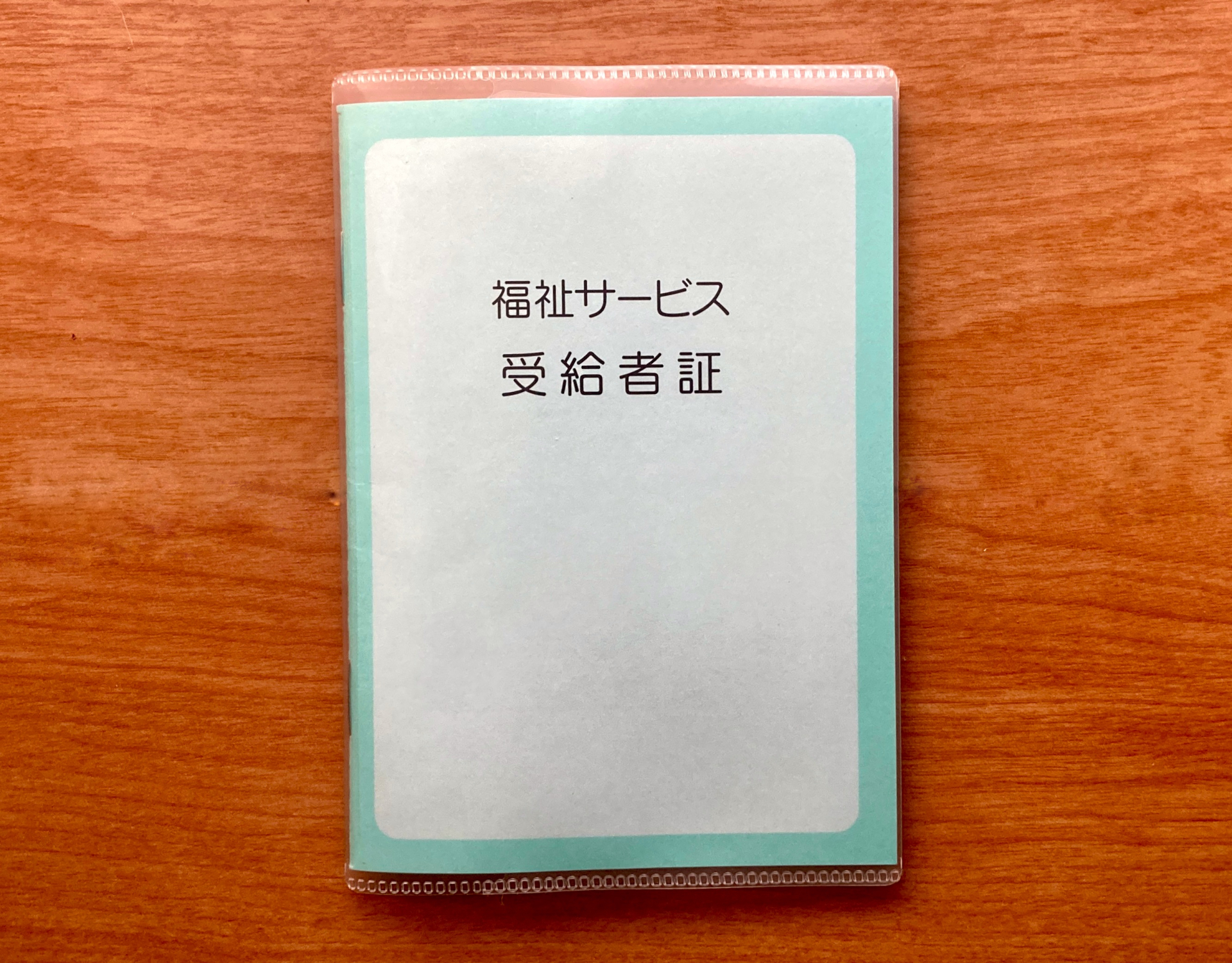
受給者証は、福祉サービスや医療サービスを公的支援で利用するために、市区町村から交付される証明書です。児童発達支援や放課後等デイサービスをはじめ、支援を必要とする多くの場面で提示が求められます。
ここでは、受給者証の種類や療育手帳(障害者手帳)との違いを解説します。
受給者証のおもな種類と役割
受給者証は、障がい福祉や医療サービスを利用するために必要な「給付の資格証明書」です。福祉サービスで必要な受給者証は、下記のとおりです。
- 通所受給者証
- 障害児入所受給者証
- 地域生活支援事業受給者証
- 障害者福祉サービス受給者証
おもに、児童発達支援や放課後等デイサービスを利用する際に使われます。また、医療サービスでは自立支援医療受給者証や障害者医療費受給者証などがあり、診療費の助成に活用されています。
受給者証は、障がいの有無を証明するのではなく、サービスの利用資格を示すための書類です。受給者証には、利用可能なサービスの種類や支給量などが記載されており、一般的には支援を受ける際に事業所へ提示して契約を行います。
療育手帳(障害者手帳)との違い
受給者証とよく混同されがちなのが、障害者手帳(療育手帳など)です。療育手帳は、知的障がいのある方に対して都道府県が発行するもので、障がいの名称や程度を証明する役割があります。
一方、受給者証は福祉サービスの利用資格を証明するもので、障がいの程度や種類を示すものではありません。したがって、障害者手帳を持っていなくても、必要性が認められれば受給者証を申請・取得が可能です。
また、障害者手帳には下記の3種類があり、それぞれ目的や交付主体が異なります。
- 身体障害者手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
- 療育手帳受給者証
障害者手帳は、用途が異なる別の書類として理解しておきましょう。
支給日数(支給量)とは
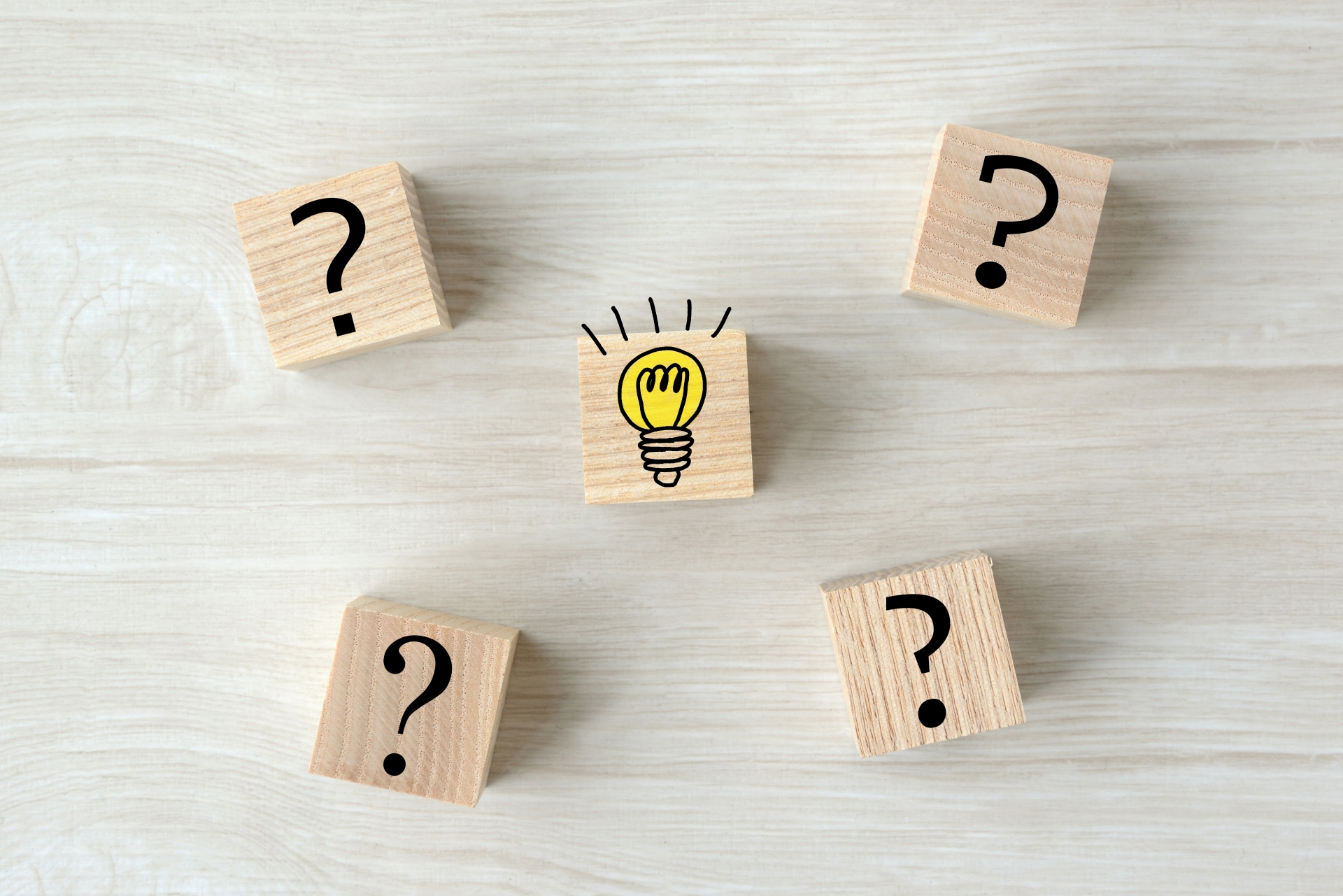
ここでは、受給者証に記載されている支給日数(支給量)について解説します。
- 福祉サービスを利用できる上限日数のこと
- 支給上限日数を超えての利用はできる?
詳しく見ていきましょう。
福祉サービスを利用できる上限日数のこと
支給日数(支給量)とは、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを、月に何日まで利用できるかを示す目安です。たとえば、支給量が「15日」と記載されていれば、その月は最大で15日まで通所できます。
支給量の上限は、原則として月23日までと厚生労働省により定められており、上限を超えての利用はできません。障がいの程度や家庭状況、保護者の就労有無などをもとに必要性が判断され、自治体が決定します。
申請の際は、障害児支援利用計画を提出する必要があり、その計画をもとに支給日数が割り当てられる仕組みです。
支給上限日数を超えての利用はできる?
原則、福祉サービスの利用は受給者証に記載された支給量の範囲内で行う必要があります。しかし、やむを得ず上限を超える利用が必要となる場合もあるでしょう。
具体的には、家庭の急な事情や保護者の勤務状況の変化、支援ニーズの増加などが該当します。このようなケースでは、まず相談支援事業所に相談し、市区町村に「支給量変更申請」を行うことが可能です。
必要性が認められると、支給量の見直しや一時的な利用許可が下りることも。ただし、あくまで例外的な対応のため、変更が必要になった時点で早めに自治体と連携し、手続きを進めることが大切です。
受給者証が必要な理由
受給者証が必要な理由は、下記のとおりです。
- 放課後等デイサービスや児童発達支援を利用できる
- 保育所や学校などでの訪問支援にも対応できる
- さまざまな施設で割引が適用される
詳しく解説します。
放課後等デイサービスや児童発達支援を利用できる
受給者証があると、児童福祉法にもとづいた障がい児通所支援である「児童発達支援」や「放課後等デイサービス」を利用できます。児童発達支援は、未就学の子どもを対象としたサービスで、日常生活の基礎を整える支援が中心です。
放課後等デイサービスは、小学生から高校生までの就学児が対象です。放課後や長期休暇に、生活スキルや社会性を高めるトレーニングを受けられます。どちらも、早期の療育や継続的な発達支援の場として重要な役割を果たします。
関連記事:放課後等デイサービスはグレーゾーンの子どもも利用できる?支援内容や選び方とは
保育所や学校などでの訪問支援にも対応できる
受給者証を取得すると、保育所等訪問支援と呼ばれるサービスも利用可能です。
この支援では、専門スタッフが保育園や幼稚園、小学校などの教育機関を訪問します。そして、障がいのある子どもへの個別支援や、周囲の先生・保育士への支援方法のアドバイスを行うのが一般的です。
集団生活の中で困りごとを抱えやすい子どもにとって、安心して通園・通学するためのサポートにつながります。訪問支援は、子どもだけでなく周囲の理解を深める意味でも効果的です。
関連記事:放課後等デイサービスは意味がない?メリット・デメリットを徹底解説
さまざまな施設で割引が適用される
受給者証には、福祉サービス利用だけでなく、生活面でのメリットもあります。自治体によっては受給者証を提示すると、日常生活を支える制度が利用できる場合があります。具体的には、下記のとおりです。
- 公共交通機関の割引
- 福祉タクシー券の交付
- 公営施設(動物園・博物館・水族館など)
また、医療費の自己負担額が軽減される「障害者医療費助成制度」の対象となるケースもあります。自治体によって内容や対象施設は異なりますが、受給者証があることで、外出のハードルが下がり、家庭全体の生活の質を高められるでしょう。
関連記事:放課後等デイサービスの利用料金と基本的な仕組みを解説
受給者証(通所受給者証)の申請対象
受給者証(通所受給者証)の申請対象者は、下記のとおりです。
- 身体障がい・知的障がい・精神障がい(発達障がいを含む)のある児童
- 厚生労働省が指定する難病を抱える児童
ただし、これらの障がいに該当しない場合でも、医師や専門機関による「支援の必要性」が認められれば申請は可能です。療育手帳や明確な診断がなくても、意見書や検査結果をもとに支給が決定されるケースもあります。
自治体の窓口や相談支援事業所に相談し、どのような書類が必要かを確認しましょう。
発達障がいやグレーゾーンの子どもも対象になる?
明確な診断名がついていない、いわゆる「グレーゾーン」の子どもでも、受給者証を申請できる可能性は十分にあるでしょう。
落ち着きのなさや集団行動の苦手さ、言葉の遅れなどが見られ、家庭や園・学校からの支援が必要な場合には、専門家の意見書をもとに申請が認められることがあります。実際には療育手帳を持っていないまま、児童発達支援や放課後等デイサービスを利用している子どもも多くいます。
必要書類や申請要件は自治体によって異なるため、児童発達支援センターや福祉課に相談し、必要な検査や意見書の取得について情報を集めましょう。
受給者証の申請から取得までの流れ

受給者証の申請から取得までの流れは、下記のとおりです。
- 施設見学や支援の相談
- 自治体の福祉課に相談
- 受給者証の申請書を提出
- 利用の必要性や支給量の決定
- 受給者証(通所受給者証)発行
手順ごとに詳しく解説します。
施設見学や支援の相談
児童発達支援や放課後等デイサービスなど、利用を検討している事業所を見学しましょう。まだ受給者証がなくても、見学や相談は可能です。
事業所の雰囲気やスタッフとの相性、通いやすさなどを確認し、子どもに合った環境を選ぶことが大切です。見学を通して「どのような支援が必要か」も整理されるため、そのあとの申請に役立ちます。
また、まだ医師に相談していない場合は、診察を受けて支援の必要性を相談しておくとスムーズに進められます。
自治体の福祉課に相談
施設見学のあとは、お住まいの市区町村の福祉課や障がい福祉窓口に相談しましょう。受給者証の申請方法や必要書類、支援計画案の作成方法などを説明してもらえます。
相談支援事業所を紹介してもらうことも可能です。はじめて申請する場合は、相談支援専門員のサポートを受けながら準備を進めることで、書類の不備や手続きの遅れを防ぎやすくなります。
受給者証の申請書を提出
準備が整ったら、必要書類とともに受給者証の申請を行います。
中心となるのは「障害児支援利用計画案」です。子どもにどのような支援が必要かを記載した計画書で、相談支援事業所に作成を依頼するか、保護者自身が作成する「セルフプラン」の提出も可能です。
ただし、一部の自治体ではセルフプランでは申請できない場合もあるため、事前に確認しておきましょう。そのほかに、意見書や所得に関する書類なども必要です。
利用の必要性や支給量の決定
申請後は、市区町村による審査・調査が行われます。調査員が家庭を訪問し、保護者や子どもの状況について聞き取り調査(アセスメント)を実施します。
下記について総合的に確認し、福祉サービスの必要性を評価する仕組みです。
- 家庭環境
- 保護者の就労状況
- 医師の意見書
- 過去の支援歴
その際に、月あたり何日利用できるか(支給量)が決定されます。支援が急を要する場合は、支給量を多めに設定してもらえる可能性もあるため、正直に現状を伝えましょう。
受給者証(通所受給者証)発行
審査の結果、福祉サービスの利用が妥当と判断されると、受給決定通知書とともに通所受給者証が発行されます。受給者証には、下記の内容が記載されています。
- 利用できるサービスの種類
- 支給日数
- 有効期限
- 自己負担額の上限
受け取ったら、事業所と正式に契約を結び、支援の利用開始です。
受給者証の申請に必要な書類一覧

受給者証の申請時には、複数の書類をそろえる必要があります。一般的には、下記5点が必要です。
- 支給申請書
- 障害児支援利用計画案(セルフプランも可)
- 医師の意見書や障害者手帳などの支援根拠
- 負担上限月額の算定に必要な世帯状況申告書・課税証明書
- マイナンバーが確認できる書類(保護者と子ども)
これらは自治体によって細かな違いがあるため、申請前に必ず窓口や公式サイトで最新の情報を確認しましょう。
受給者証の取得にかかる期間の目安
受給者証の申請から発行までには、2週間~2ヶ月程度かかります。自治体や申請時期によってはさらに時間を要することもあるため、利用希望日の2ヶ月前を目安に申請準備をはじめると安心です。
とくに年度末や新年度前は混み合いやすいため、早めの行動をしましょう。
また、受給者証が発行されても、希望する施設の空き状況によってはすぐに利用開始できない場合も。事業所とも並行して相談しておくとよいでしょう。
受給者証は更新が必要!期限切れに注意
受給者証には有効期限があり、原則として1年ごとの更新が必要です。有効期限は子どもの誕生月や年度末など、自治体により異なるので注意が必要です。
更新手続きは支給終了日の3ヶ月前から開始でき、多くの自治体では1~2ヶ月前に更新案内が郵送されます。なお、入学や進学によりサービス内容が変わる際にも、更新・変更が必要になるケースがあります。
更新を忘れるとサービスが一時的に利用できなくなるため、余裕を持って準備を進めましょう。
受給者証を取得して、安心して福祉サービスを活用しよう
受給者証があれば、児童発達支援や放課後等デイサービスを公的支援のもとで利用でき、子どもの発達を多角的にサポートできます。はじめての申請でも、必要なステップを知っておくことで安心して進められるでしょう。
「ちゃれんじくらぶ」では、子どもの個性と成長段階に合わせた多様なカリキュラムを用意しています。保護者との連携を大切にしながら、継続的な成長支援を提供しています。
安心して任せられる療育環境をお探しの方は、ぜひ一度ご相談ください。
この記事の監修者
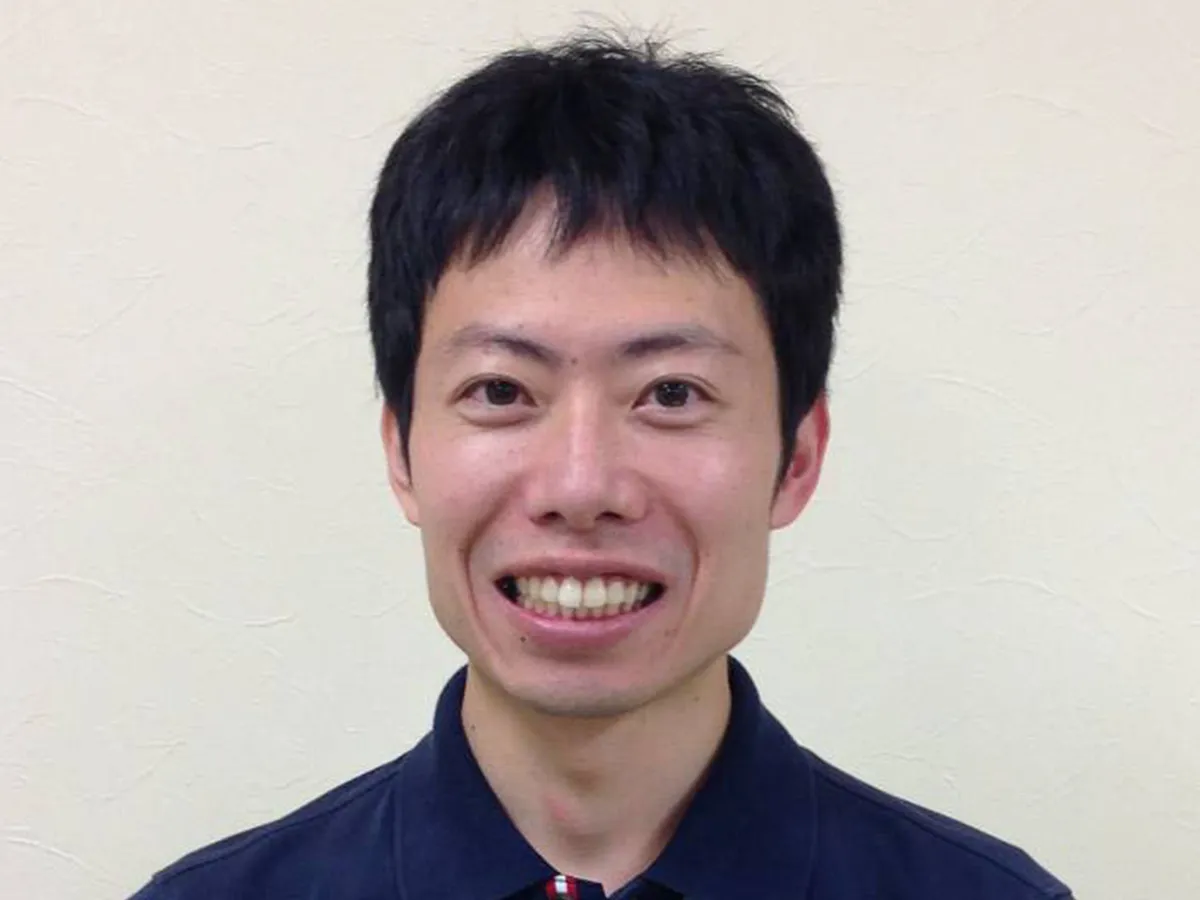
《略歴》
理学療法士免許取得後、医療・介護分野にて回復期や慢性期、通所リハなど多様な現場経験を経て、リハビリ型デイサービスや訪問看護、児童を含む福祉施設の立ち上げおよび運営サポートに従事。
現在は業界歴17年の実績を活かし、放課後等デイサービス「ちゃれんじくらぶ」の運営をサポートしている。
《役職》
三州資材工業株式会社 統括部 総合福祉責任者
株式会社IQOL 取締役
《保有資格》
理学療法士、介護支援専門員、防火管理責任者、介護労働者雇用管理責任者、食品衛生責任者、強度行動障害支援者











