放課後等デイサービスの利用料金と基本的な仕組みを解説

子どもの発達支援において、重要な役割を持つ放課後等デイサービス。
しかし、料金や仕組みについて気になる方もいるのではないでしょうか。
この記事では、放課後等デイサービスにおける利用料金と仕組みについて、詳しく解説します。
放課後等デイサービスの利用を検討中の方は、ぜひ参考にしてください。
放課後等デイサービスとは
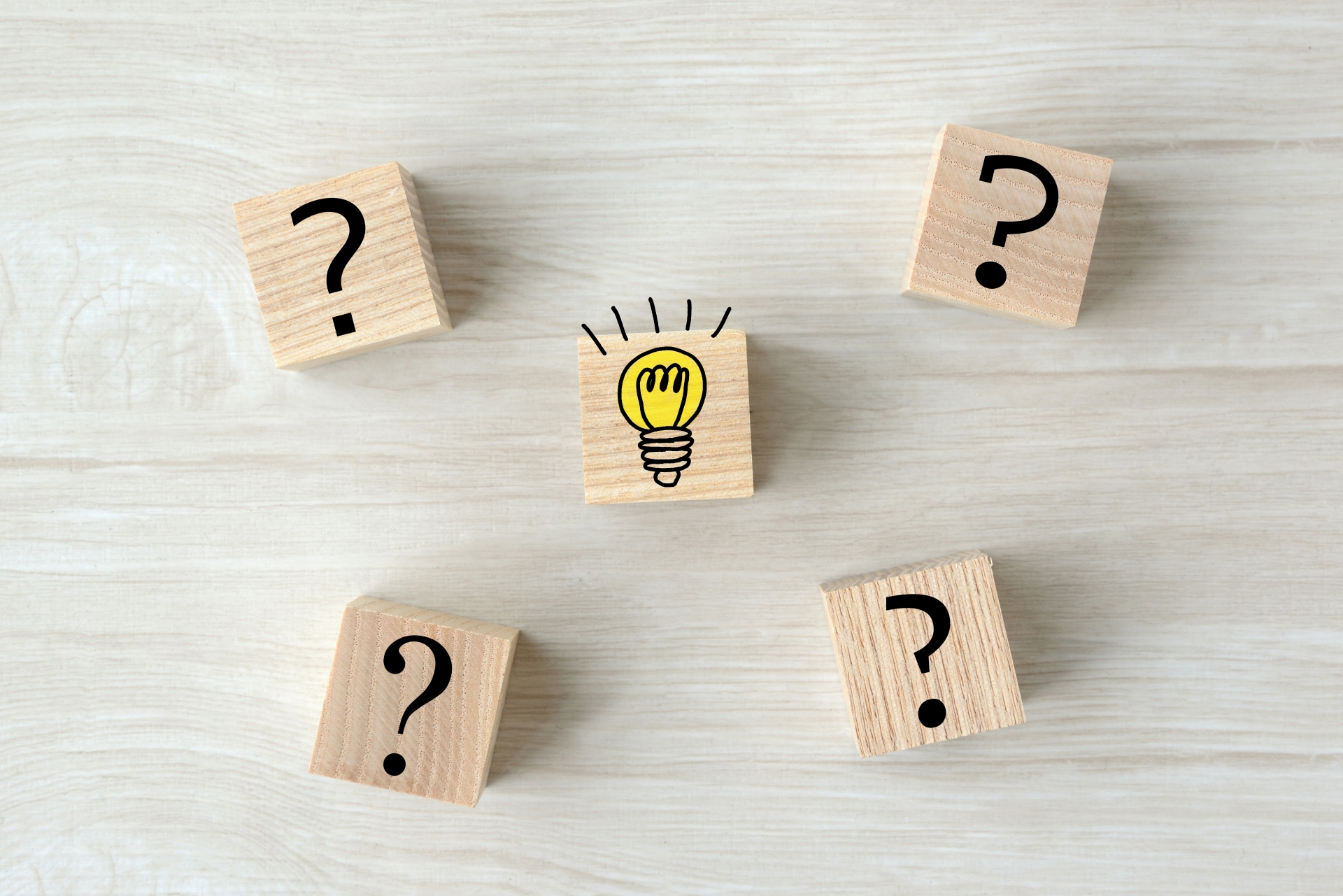
放課後等デイサービスとは、児童福祉法に基づく通所型の福祉サービスです。障がいのある学齢期の子どもに対して、生活能力向上のための訓練や社会との交流促進などを目的とした活動を提供します。
一人ひとりの状況や発達段階に合わせて、きめ細やかな支援が行われるのが特徴です。子どもたちは放課後や学校がお休みの日に通所し、学びや遊びを通して社会的なスキルや才能を磨きます。
関連記事:放課後等デイサービスとは?支援内容や利用する手順を解説
放課後等デイサービスの利用料金の仕組み

放課後等デイサービスの利用料金の仕組みについて、以下の3つの内容を解説します。
- 国や自治体が利用料金の9割を補助する
- 世帯に応じて負担上限額の区分がある
- 自治体によって助成が受けられることもある
それぞれ確認していきましょう。
国や自治体が利用料金の9割を補助する
放課後等デイサービスの利用料金は、原則としてサービス費用の1割が利用者の自己負担額になります。残りの9割は公費によって国と自治体が負担する仕組みです。
このように、経済的な理由で必要な支援を諦めることのないよう、障がいのある子どもの成長を社会全体で支える仕組みが整っています。
世帯に応じて負担上限額の区分がある
放課後等デイサービスの利用料金は、世帯の所得状況に応じて負担上限額が設定されています。
利用回数が多い場合でも一定額以上の負担は生じません。負担上限額の区分は以下のとおりです。なお、世帯年収は、前年度の所得に基づいて計算されます。
| 世帯所得に応じた上限額 | |
| 生活保護世帯・市民税非課税世帯 | 0円 |
| 市民税課税世帯 | 4,600円 |
| 年収約920万円以上の世帯 | 37,200円 |
上限額を超えてサービスを利用した場合でも、支払う金額は上限額までです。ただし上記は一般的な区分であり、自治体によって多少異なる場合もあります。事業所によっては、別途実費が必要になることがあるため、あらかじめ確認しておきましょう。
自治体によって助成が受けられることもある
お住まいの自治体によっては、独自の助成制度を設けている場合があります。自治体の助成制度は、国の制度とは別に実施されているものです。
たとえば、送迎サービスがない場合の交通費の一部補助や、利用料金の減免などが該当します。利用する自治体で助成制度があるか、対象となる条件や内容、申請方法などをチェックしておきましょう。
放課後等デイサービス利用における追加費用

放課後等デイサービスでは、利用料金の9割が補助されます。ただし、以下のような実費での負担が必要な費用もあります。
- おやつ代
- 活動費
- 持ち物代
- キャンセル料
それぞれ見ていきましょう。
おやつ代
放課後等デイサービスでは、利用時間中におやつが提供されることもあります。おやつ代は、利用料と別に実費で徴収されるのが一般的です。
おやつの内容や事業所の方針によって異なりますが、1回あたり50円~150円程度が目安になります。月額固定のほか、利用日数に応じて変動する場合があるため、契約時に確認しておくとよいでしょう。
活動費
放課後等デイサービスでは、日常生活訓練や創作活動、地域交流など、さまざまな活動プログラムが提供されています。これらの活動に必要な材料費や施設利用料、交通費などが活動費として実費で徴収される場合があります。
持ち物代
放課後等デイサービスの利用にあたって、事業所から指定された持ち物にかかる費用です。たとえば、以下の持ち物の準備が必要になる場合があります。
- 着替え
- タオル
- 上履き
- 水筒
- 教材
これらの持ち物は基本的に保護者が用意するため、その購入費用は実費での負担です。一部の事業所では、特定の持ち物を事業所側で用意し、その費用を実費徴収する場合もあります。
キャンセル料
放課後等デイサービスは障がいのある児童が通う施設であるため、体調不良等によって急遽欠席することも少なくありません。放課後等デイサービスにおけるキャンセル料は、急な欠席によって生じる事業所の損失を補填する目的で設定されています。
体調不良や急な事情による欠席については、キャンセル料が免除される場合もありますが、事業所によって異なります。キャンセル料の規定は、契約書や重要事項説明書に明記されているため、契約前に確認が必要です。
放課後等デイサービスの利用料金の例
ここから、世帯状況や利用日数などを仮定した料金の例をいくつか紹介します。
| 【市民税課税世帯、週3回利用の場合】
サービス利用料(月12回利用):1回あたり800円(800×15=9,600円) 月額上限額(市民税課税世帯): 4,600円 おやつ代(実費): 1回あたり50円(50×12=600円) 活動費(実費): 月額1,500円 合計:6,700円
サービス利用料は本来9,600円ですが、上限額が適用され4,600円になります。 これにおやつ代600円、活動費1,500円が加わり、合計で6,700円です。 |
| 【生活保護世帯・市民税非課税世帯、月15回利用の場合】
サービス利用料:0円 おやつ代(実費): 1回あたり50円(50×15=750円) 活動費(実費):月額1,000円 合計:1,750円
生活保護世帯や市民税非課税世帯では、サービス利用料の自己負担はありません。おや |
| 【年収約920万円以上の世帯、週3回利用の場合】
サービス利用料(月12回利用): 1回あたり800円(800×15=9,600円) 月額上限額(一定所得以上世帯): 37,200円 おやつ代(実費): 1回あたり50円(50×12=600円) 活動費(実費): 月額1,000円 合計:11,200円
この場合、1割負担額が上限額を下回っているため、サービス利用料は9,600円、実費と |
実際の利用料金は、利用する日数やサービス内容、世帯所得、自治体の制度などによって大きく変動します。料金の詳細について把握するには、利用する事業所に問い合わせて、具体的な費用を確認しましょう。
放課後等デイサービスを賢く利用するポイント
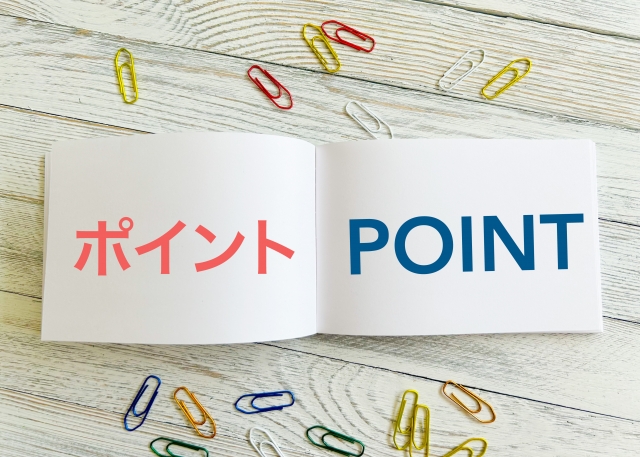
放課後等デイサービスは、子どもの発達支援において重要な役割を果たします。効果的にサービスを活用するには、いくつかのポイントを押さえることが大切です。
- 自治体のルールや助成制度を確認する
- 複数の放課後等デイサービスを比較する
- 利用する頻度とコストのバランスを考える
それぞれ詳しく解説します。
自治体のルールや助成制度を確認する
国が定める基本的な制度に加えて、自治体によっては利用料の減免や交通費の補助など、独自の支援策を設けている場合があります。本来受けられるはずの支援を見過ごさないためにも、自治体の制度やルールについて調べておくことが大切です。
自治体の障害福祉に関する情報を確認することで、利用料金を抑え、より賢くサービスを活用できるでしょう。また、自治体によっては、独自の相談窓口を設けていたり、地域の事業所と連携したプログラムを提供していたりすることもあります。
これらの情報を事前に把握しておくことで、スムーズに利用を開始できるだけでなく、子どもにとっても最適な選択肢が選べます。
複数の放課後等デイサービスを比較する
放課後等デイサービスは、それぞれに特色や強みがあります。提供されるプログラム内容、得意とする支援、施設の雰囲気などが大きく異なるため、複数の事業所を比較検討することが大切です。
子どもの個性や発達段階、抱える課題やニーズを十分に考慮したうえで、もっとも適した支援を提供してくれる事業所を選択しましょう。パンフレットやWebサイトだけでなく、実際に事業所を訪れることで、実際の雰囲気を知る手がかりになります。
可能であれば見学だけでなく、体験での利用を申し込むのがおすすめです。 実際に事業所の活動に参加することで、子どもの適性や事業所の支援内容との相性を見極められます。
関連記事:放課後等デイサービスは不登校でも利用できる?出席扱いになる方法とは
利用する頻度とコストのバランスを考える
放課後等デイサービスの利用頻度を決める際には、子どもの発達状況や課題、家庭の状況などを総合的に考慮する必要があります。障害児通所受給者証の交付を受ける前に、事業所や自治体の相談支援専門員と、子どもにとって必要な支援内容や適切な利用回数について十分に話し合うとよいでしょう。
障害児通所受給者証には、利用できる上限日数が記載されます。世帯状況によっては、利用頻度が高いと月額の負担が大きく感じられるかもしれません。
また、放課後等デイサービスの利用頻度は、固定されたものではありません。子どもの成長や状況の変化に合わせて柔軟に見直すことが大切です。学校生活が落ち着いてきた時期や、特定のスキルを集中的に伸ばしたい時期など、必要に応じて利用頻度は調整できます。
事業所のスタッフや専門家と相談しながら、子どもの発達段階や課題、家庭の状況を総合的に判断し、最適な利用頻度を検討することで、より効果的な支援を受けられるでしょう。
放課後等デイサービスに関するよくある質問
放課後等デイサービスに関する、よくある質問についてお答えします。
- 放課後等デイサービスの1日の利用料金はいくらですか?
- 兄弟が放課後等デイサービスを利用する場合の料金について教えてください
- 複数の放課後等デイサービスを利用する場合、料金はどうなりますか?
放課後等デイサービスの1日の利用料金はいくらですか?
具体的な1日の利用料金については、利用を検討している事業所に、直接お問い合わせされるのがもっとも確実です。1日の利用料は、提供する支援内容や時間、適用される加算によって異なります。
お住まいの自治体の福祉担当窓口や相談支援事業所でも、一般的な料金体系について情報を得られる場合があります。事業所や自治体に問い合わせる際は、子どもの状況や希望する利用回数などを具体的に伝えることで、より正確な料金を知る手がかりになるでしょう。
兄弟が放課後等デイサービスを利用する場合の料金について教えてください
兄弟で放課後等デイサービスを利用される場合の料金については、原則として1人ずつに利用料金が発生します。ただし、世帯ごとの月額負担上限額が適用されるため、ご兄弟の利用料金の合計が上限額を超えた場合は、それ以上の自己負担はありません。
また、サービス利用料とは別に発生するおやつ代や活動費などは、子どもの人数分必要です。料金の詳細は事業所によっても異なるため、直接ご確認ください。
複数の放課後等デイサービスを利用する場合、料金はどうなりますか?
利用したそれぞれの事業所に対して、利用日数や時間に応じたサービス費用の1割の自己負担が発生します。ただし複数の事業所で、利用料金の合計額が世帯の上限額を超える場合、支払う金額はその上限額までです。
複数の事業所を利用する場合は、障害児通所受給者証の利用可能日数を確認し、計画的に利用しましょう。
まとめ:利用料金についての不安や疑問は事業所に相談してみましょう
放課後等デイサービスは、障がいのある子どもの成長を支援する福祉サービスです。子どもの健やかな成長を支えるためにも、利用料金のほか、事業所の取り組みや支援プログラムなど、気になる点について情報収集を行うことが大切です。
また、自治体の窓口や相談支援事業所では、地域の放課後等デイサービスの情報だけでなく、利用料金に関する一般的な仕組みや、利用可能な助成制度について教えてもらえることもあります。
これらの情報源を有効活用し、安心して利用できる準備を整えましょう。お子様が安心して過ごせる居場所や、成長を促す専門的な支援をお探しなら「ちゃれんじくらぶ」も一度ご検討ください。疑問点や不安なことがあれば、いつでもご相談いただけます。
この記事の監修者
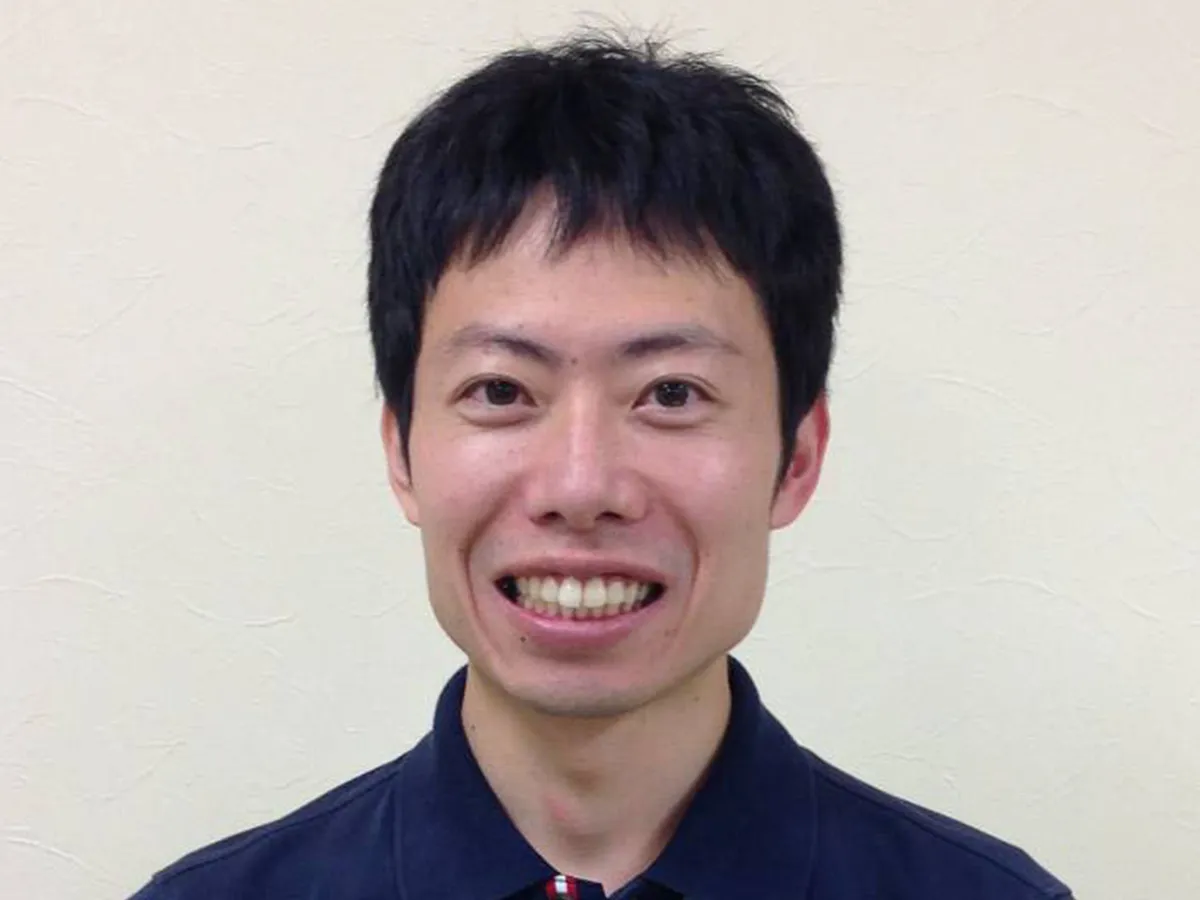
《略歴》
理学療法士免許取得後、医療・介護分野にて回復期や慢性期、通所リハなど多様な現場経験を経て、リハビリ型デイサービスや訪問看護、児童を含む福祉施設の立ち上げおよび運営サポートに従事。
現在は業界歴17年の実績を活かし、放課後等デイサービス「ちゃれんじくらぶ」の運営をサポートしている。
《役職》
三州資材工業株式会社 統括部 総合福祉責任者
株式会社IQOL 取締役
《保有資格》
理学療法士、介護支援専門員、防火管理責任者、介護労働者雇用管理責任者、食品衛生責任者、強度行動障害支援者











