放課後等デイサービスと児童発達支援の療育の違いとは?おもな療育の種類も解説

障がいをお持ちのお子さまのための支援施設に「放課後等デイサービス」と「児童発達支援」があります。
この記事では、放課後等デイサービスと児童発達支援の療育の目的と期待される効果、具体的な違いを解説します。
おもな療育の種類にも触れていますので、お子さまの成長や発達をサポートしたいと考えている親御さんは、ぜひ参考にしてください。
療育の目的・期待する効果

療育の目的は、障がいを持つ子どもが自立した生活を送るために、必要なスキルや社会的な能力を身につけることです。ここでは、2つの支援サービスの概要を説明します。
- 放課後等デイサービス
- 児童発達支援
それぞれ見ていきましょう。
放課後等デイサービス
放課後等デイサービスの療育は、おもに小学校入学から高校卒業までの年齢層が対象です。放課後や休日の通所が一般的で、社会生活に必要なスキルやコミュニケーション能力を養うためのプログラムが提供されます。
たとえば、グループ活動を通じてほかの子どもと協力しながら学ぶ機会が多く、自己肯定感の向上やストレスの軽減も期待できます。
関連記事:放課後等デイサービスとは?支援内容や利用する手順を解説
関連記事:放課後等デイサービスは意味がない?メリット・デメリットを徹底解説
児童発達支援
児童発達支援は、未就学児が対象です。子ども一人ひとりの発達段階や特性に応じた個別の支援計画が作成され、日常生活のスキルや社会的な能力を伸ばすための療育が行われます。
遊びを通じた学びや感覚統合療法などの専門的なプログラムが用意されており、子どもが楽しく学びながら成長できる環境が整っています。これにより、自信を持って社会生活を送るための基盤を築けることが特徴です。
放課後等デイサービスと児童発達支援の療育の違い

ここでは、放課後等デイサービスと児童発達支援の3つの違いを説明します。
- 対象年齢
- 利用料金
- 指導方針
それぞれ見ていきましょう。
対象年齢
児童発達支援は、おもに未就学児(0~6歳まで)が対象です。一方、放課後等デイサービスは、小学生から高校生までの就学児(6~18歳まで)が対象です。
なお、自治体によっては20歳まで利用可能な場合もあります。たとえば、特別な支援や進学準備のサポートが必要な場合があげられます。
利用料金
児童発達支援と放課後等デイサービスの利用料金は、基本的に国や自治体が9割を補助し、利用者は1割を負担します。ただし、所得に応じて利用者負担額の上限が設定されているため注意が必要です。
また、3~5歳までの利用者は無償化される場合もあります。具体的な費用は、厚生労働省の公式サイトを参考にするとよいでしょう。
|
所得区分 |
月額上限額 |
| 生活保護受給世帯 |
0円 |
| 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
| 市町村民税課税世帯
(所得割28万円未満) |
通所施設、ホームヘルプ利用の場合:4,600円
入所施設利用の場合:9,300円 |
| 上記以外 | 3万7,200円 |
指導方針
児童発達支援は、未就学児が日常生活や社会生活に必要な基本的なスキルを身につけることを重視します。これに対して、放課後等デイサービスは、学齢期の子どもが学校や社会で必要とされるスキルを養うことに重点を置きます。
以下に、指導方針の違いをまとめました。
|
児童発達支援 |
放課後等デイサービス |
| ・着替えや食事
・片付けなどの自立訓練 ・身体機能の向上 |
・対人関係や自己管理のスキルの向上
・学校の勉強や将来の就職に関する支援 |
このように、それぞれの対象年齢やニーズに応じた支援が提供されます。利用を検討する際には、子どもの成長段階や特性を考慮することが大切です。
おもな療育の種類

療育にはさまざまな方法がありますが、子どもの特性やニーズに応じて適した方法を選ぶことが重要です。ここでは、代表的な療育を7つ紹介します。
- 応用行動分析(ABA)
- TEACCH
- ソーシャルスキルトレーニング(SST)
- 認知行動療法(CBT)
- 作業療法(OT)
- 音楽療法
- 感覚統合療法
ぜひ、どの療育がもっとも子どもに適しているか参考にしてください。
応用行動分析(ABA)
行動の前後を分析して適切な行動を増やす方法です。使用する基本原理は「強化」「弱化」「消去」の3つです。
たとえば、子どもが宿題をやりとげたあとに褒めると、よい行動を継続しやすくします。また、問題行動のあとにご褒美を与えないことで、ダメな行動を減らします。
日常の中で好ましい行動に対して、即座に肯定的なフィードバックを与える手法が用いられていることが特徴です。特定の行動を改善したい子どもにおすすめです。
TEACCH
自閉症やコミュニケーションに課題のある子どもに対して、視覚的な情報を活用して支援する方法です。日常生活をスムーズに送れることを目指します。
たとえば、朝のルーチンを写真や絵カードで見せ、子どもが1日の流れを視覚的に理解しやすくします。
これにより、子どもは何をすべきか明確に理解し、安心して活動に取り組むことが可能です。とくに、自閉症スペクトラムの子どもに効果を発揮します。
ソーシャルスキルトレーニング(SST)
社会的なスキルを育成するためのトレーニングです。たとえば、友達との遊び方や適切な会話方法をロールプレイで学びます。グループディスカッションや模擬的な社会状況の演習が行われ、人間関係のスキルを高めることが目的です。
このトレーニングにより、ストレス軽減やトラブル予防などの効果が期待でき、日常生活や学校生活での対人関係に役立ちます。とくに、他者と適切な距離感をつかめず、感情のコントロールが難しいと感じている子どもに適しています。
認知行動療法(CBT)
考え方や物事の捉え方に働きかけ、感情や行動を調整する方法です。不安を感じたときに「これは一時的なもの」と考えることで気持ちを落ち着けます。
たとえば、子どもと一緒にネガティブな思考をポジティブなものに置き換える練習を行います。思考記録表によりネガティブな考えを可視化し、ポジティブな面を見つける方法や、緊張をほぐす方法が効果的です。
これにより、不安やストレスが軽減され、ポジティブマインドにつながります。心理的な問題を抱える子どもにおすすめです。
作業療法(OT)
日常生活の活動を通じて、身体機能や社会性を高める方法です。たとえば、手先の器用さを高めるためにビーズを使った工作を行います。バランスボールや跳躍器具を使った運動もおすすめです。
これにより、身体のコントロールやバランス、協調性が改善されます。子どもが楽しめる活動が多いため、モチベーションの向上やストレス解消の効果も期待できます。
身体の発達や運動能力が課題な子どもにおすすめで、積極的に取り組める活動を通じて成長のサポートが可能です。
音楽療法
音楽を通じて情緒やコミュニケーション能力を向上させる方法です。たとえば、楽器を使ったリズム遊びや、歌唱による感情表現があげられます。
また、曲に合わせて体を動かしたり、歌詞を読み上げながらコミュニケーションをとったりする方法も含みます。音楽によるリラックス効果も得られることが特徴です。
感覚統合療法
感覚統合療法は、感覚情報の処理を改善するための方法です。触覚過敏の子どもに対して、さまざまな触感のものを触らせることで感覚を慣らします。スイングやボールプール、触覚マットを使った活動がおすすめです。
触覚過敏があると、衣類の着用や食事の際に支障をきたすため、日常生活の質に影響します。子どもが無理なく楽しみながら取り組めるように、活動の進め方にはとくに注意が必要です。感覚過敏や感覚鈍麻がある子どもにおすすめです。
放課後等デイサービスの療育プログラム例
放課後等デイサービスでは、子どもの発達を支援するためにさまざまな療育プログラムが提供されています。ここでは、代表的なプログラム例を3つ紹介します。
- 社会性を育むグループ活動
- 学習支援・宿題サポート
- 創造力を高めるアート・クラフト活動
それぞれ見ていきましょう。
関連記事:受給者証とは?必要な理由や放課後等デイサービスの申請方法を解説
社会性を育むグループ活動
グループ活動を通じて、コミュニケーションスキルや協調性を育むことが目的で、チームでの活動により、他者との関わり方を学びます。ほかの子どもとの交流や協力が苦手な子どもや、人間関係のスキルを高めたい子どもにおすすめです。
以下にプログラムの例をまとめました。
|
プログラム例 |
詳細 |
|
チームビルディングゲーム |
チームで協力して課題を解決するゲーム |
|
共同制作プロジェクト |
みんなで一緒に大きな絵を描いたり、クラフトを作った |
|
ロールプレイング |
さまざまな社会的状況を模擬的に演じる活動 |
上記のプログラムの実践により、コミュニケーション能力の向上や協調性の育成、社会性の発達が期待できます。
これにより、子どもは他者との関わりに自信を持て、社会での適応能力が高まります。
学習支援・宿題サポート
放課後の時間を利用して、学校の宿題や学習を支援します。個別にサポートするため、子どものペースに合わせて進められることが特徴です。学校の宿題に取り組むのが難しく学習に対する自信がない子どもや、集中力が続かない子どもに向いています。
たとえば、以下のようなプログラムがあげられます。
| プログラム例 | 詳細 |
| 個別宿題サポート | 学校の宿題を一緒に取り組み、分からないところをサポートす る |
| 集中力トレーニング | 短い時間で集中力を高めるためのゲームや課題を実施し、徐々 に向上させる |
| 学習計画作成支援 | 自分で学習計画を立てる方法を教え、実行する |
上記のプログラムに参加することで、学習習慣が定着し、意欲も上がるでしょう。
これにより、子どもは学習に対する自信を持ち、自主的に取り組む力が養われます。
創造力を高めるアート・クラフト活動
絵を描いたり、工作をしたりする活動を通じて、創造力や表現力を育むことを目指します。感情の表現方法や自己表現のスキルアップも期待できます。自分の感情を表現するのが苦手な子どもや、手先の器用さを向上させることで創造的に活動したい子どもにおすすめです。
以下に創造力を育成するためのプログラムの例をあげました。
| プログラム例 | 詳細 |
| 絵画教室
|
絵の具やクレヨンを使って自由に絵を描くことで、創造力と表現力を 育てる |
| クラフト工作 | 紙や布、ビーズなどを使ってさまざまな工作を行い、手先の器用さを 向上させる |
| 陶芸体験 | 粘土を使って陶芸作品を作り、立体的な創作活動を通じて空間認識力 を鍛える |
これらの活動により、手先の器用さが向上し、創造力が養われます。
これにより、子どもは自分の感情や考えを表現する力が身につき、自信を持って創造的な活動に取り組めるようになります。
放課後等デイサービスと児童発達支援の療育の違いを理解して、子どもに合った施設を選びましょう

放課後等デイサービスと児童発達支援は、どちらも子どもの発達をサポートする役割を果たしますが、提供内容や対象年齢が異なります。子どもに最適な施設を選ぶために、それぞれの特徴を理解することが大切です。
とくに、どちらが子どもの発達段階や生活リズムに適しているかを見極めるために、専門家や施設スタッフへの相談をおすすめします。
なお、「ちゃれんじくらぶ」では、障がいを抱える子どもが自信を持って成長できるよう、さまざまなカリキュラムを提供しています。子どもの個性を大切にした療育をお考えの方は、ぜひご相談ください。
この記事の監修者
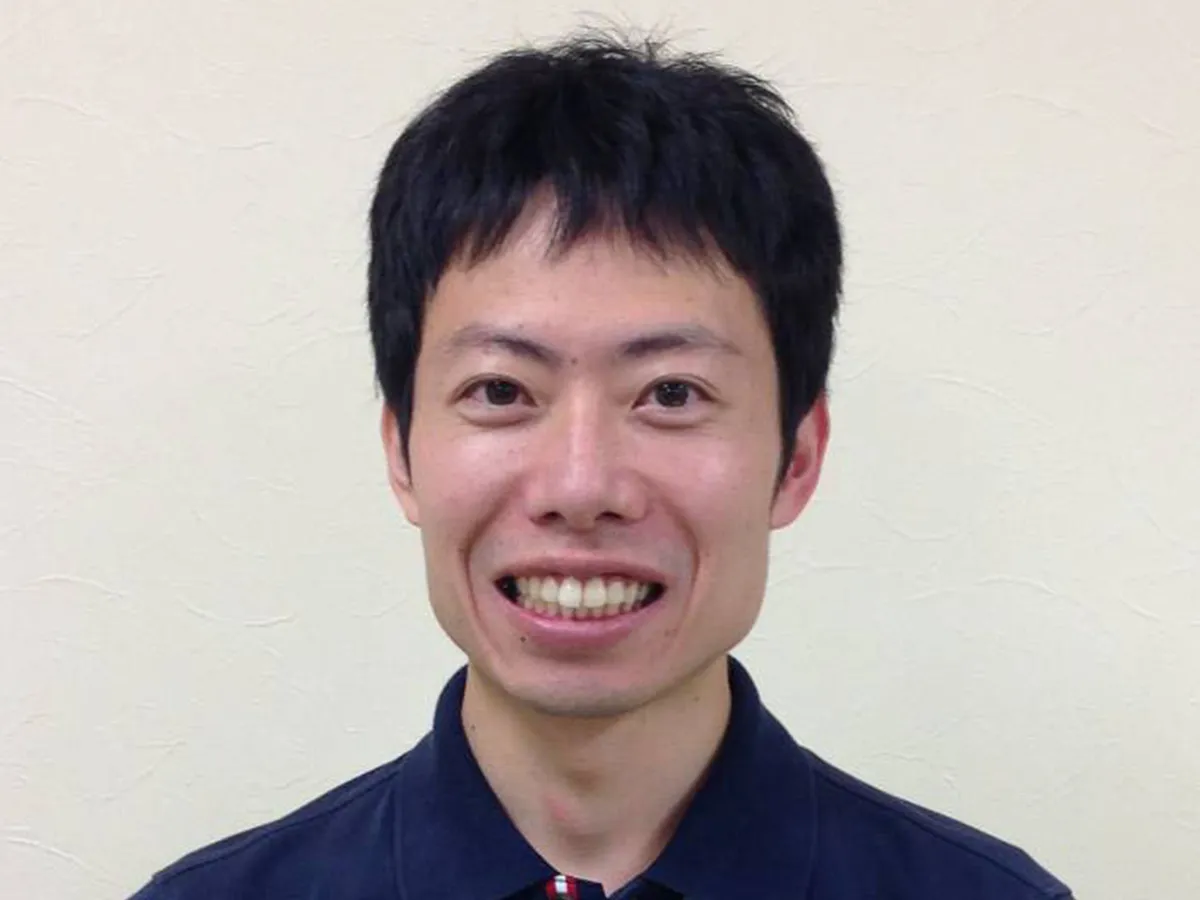
《略歴》
理学療法士免許取得後、医療・介護分野にて回復期や慢性期、通所リハなど多様な現場経験を経て、リハビリ型デイサービスや訪問看護、児童を含む福祉施設の立ち上げおよび運営サポートに従事。
現在は業界歴17年の実績を活かし、放課後等デイサービス「ちゃれんじくらぶ」の運営をサポートしている。
《役職》
三州資材工業株式会社 統括部 総合福祉責任者
株式会社IQOL 取締役
《保有資格》
理学療法士、介護支援専門員、防火管理責任者、介護労働者雇用管理責任者、食品衛生責任者、強度行動障害支援者











