放課後等デイサービスとは?支援内容や利用する手順を解説

放課後等デイサービスとは、障がいのある児童に対して、日常や集団生活への適応を支援する通所型のサービスです。
この記事では、放課後等デイサービスの支援内容や利用手順、費用などについて詳しく解説します。
放課後等デイサービスに興味のある方や、利用を検討中の方はぜひ参考にしてください。
放課後等デイサービスとは

放課後等デイサービス(放デイ)とは、障がいのある子どもが放課後や長期休暇中に利用できる福祉サービスです。児童福祉法に基づく児童通所支援事業に位置づけられます。
放課後等デイサービスの目的は、子どもの最善の利益の保障と健全な育成を図ることです。学校が終わった後や夏休みなどの長期休暇中に通所し、日常生活動作の習得や集団生活への適応に向けた支援が行われます。
放課後等デイサービスの対象者
放課後等デイサービスの対象者は、原則として就学している6歳から18歳までが対象です。例外的に18歳を超えても、サービスを利用しなければ福祉を損なうおそれがあると認められる場合は、満20歳に達するまで利用できます。
放課後等デイサービスを利用するためには、お住まいの自治体から発行される「障害者通所受給者証」が必要です。受給者証は、子どもの状況や保護者の意向などを踏まえて交付されます。利用を検討される場合は、まずはお住まいの自治体の福祉窓口や、地域の相談支援事業所に相談しましょう。
関連記事:放課後等デイサービスはグレーゾーンの子どもも利用できる?支援内容や選び方とは
関連記事:放課後等デイサービスは不登校でも利用できる?出席扱いになる方法とは
放課後等デイサービスで行われるおもな取り組み

放課後等デイサービスでは、基本的な4つの取り組みと保護者に対する支援をしています。
- 自立支援と日常生活の充実のための活動
- 創作活動
- 地域交流の機会の提供
- 余暇の提供
- 保護者に対する相談や支援
それぞれ確認していきましょう。
自立支援と日常生活の充実のための活動
放課後等デイサービスでは、利用する子どもたちが将来的に地域社会で自立し、主体的に生活していけることを目指します。自立支援と日常生活の充実のための活動は、その基盤を養うためにさまざまな支援を行う活動です。生活に必要な基本的な動作を習得し、自分でできることを増やしていきます。
具体的には、食事や手洗い、歯磨きといった基本的な動作から、買い物や公共交通機関の利用などの幅広い活動を実践します。楽しみながらさまざまな活動に取り組むことで達成感を味わうとともに、将来の就労に向けたスキルの習得につながるでしょう。
創作活動
放課後等デイサービスにおける創作活動は、子どもの表現力や創造力、集中力などを育む取り組みです。ただ作ることを目的とするだけでなく、その過程を通して自己表現の楽しさを体験し、達成感や自己肯定感の獲得につなげます。
とくに言葉でのコミュニケーションが苦手な子どもにとって、創作活動は大切な表現活動です。絵を描く、音楽を奏でる、物語を作るなど、さまざまな活動を通して、子どもたちは自分の内面を自由に表現します。
地域交流の機会の提供
放課後等デイサービスでは、地域交流の機会を提供しており、障がいのある子どもたちが地域社会の一員としてさまざまな人々と交流する機会を設けています。地域への理解を深めることも、この活動の目的の1つです。
具体的には、地域のボランティア活動への参加や図書館、公園、地域の商店などをスタッフと一緒に利用します。学校や家庭以外の社会との接点を増やすことで、子どもたちの社会参加を促進し、自立に向けた力を養います。
余暇の提供
学校や療育などの活動時間以外に、自由な時間を主体的に楽しむ時間として、余暇の提供も行います。
子どもたちにとって余暇は、多様な遊びを通して心身をリフレッシュする大切な時間です。余暇時間では、その日の気分や体調に合わせて、自由に過ごし方を選択できます。
室内では絵本やボードゲーム、パズルなどの落ち着いて楽しめる活動を用意し、屋外では、ボール遊びや鬼ごっこ、遊具など、体を動かして発散できる機会を提供します。
保護者に対する相談や支援
放課後等デイサービスでは、基本的な取り組みのほかに、保護者への支援も重要な役割としています。子どもたちの発達や特性に応じた支援を行うためには、保護者との情報共有や連携が欠かせません。
定期的な面談や連絡帳などを通してのやり取りはもちろん、家庭での困り事や課題について相談を受けることもあります。専門スタッフから具体的な関わり方や工夫についてアドバイスを受けることで、困り事やお悩みの軽減につながるでしょう。
放課後等デイサービスの1日の流れ

放課後等デイサービスの1日の流れは、施設や曜日、活動内容によって異なります。一例として、平日と長期休暇中の流れを紹介します。
学校がある日の一般的な1日の流れは、以下のとおりです。
| お迎え(学校の終了時刻)
スタッフが学校や自宅、または指定された場所へ送迎車などで迎えに行きます。
到着・余暇時間(14:00~15:00頃) 施設に到着後、手洗いやうがい、持ち物の整理などを実施。落ち着いた雰囲気の中で、
休憩・おやつ (15:00) 水分補給をしたり、おやつを食べたりする時間です。ほかの子どもやスタッフとコミュ
個別課題・集団活動(15:00~17:00頃) 個別支援計画に基づき、それぞれの目標に向けた活動(日常生活動作の練習・学習支援
帰りの準備(17:00~17:20頃) 持ち物の確認や片付けの実施。連絡帳などで、その日の活動内容や家庭での留意事項な
送迎(17:30~18:30頃) ご自宅や指定された場所まで、送迎車などで安全に送迎します。保護者の方に、その日 |
土曜日や夏休みや冬休みのような長期休暇中は、より長い時間を施設で過ごします。学校がない日の過ごし方の一例を下記に示しました。
|
お迎え(9:00~10:00) スタッフが送迎車などで自宅へ迎えに行きます。
到着・活動時間(9:00~12:00頃) 到着後に手洗いうがい、持ち物の整理を実施。スケジュールに沿って創作活動や体験学
昼食 (12:00~13:00頃) 持参したお弁当や、施設で用意した昼食をみんなで食べる時間です。調理活動の一環と
午後の活動 (13:00~16:00頃) 個別の目標に向けた活動などを実施。余暇時間として子どもが好きに活動できる時間も
帰りの準備(17:00~17:20頃) 片付けや帰り支度、1日の振り返りを行います。
送迎(17:30~18:30頃) 送迎車などで、子どもたちを安全に送り届けます。 |
放課後等デイサービスではこれらの活動を通して、家庭と連携しながら子どもたちの成長を支えています。
放課後等デイサービスを利用する手順
放課後等デイサービスを利用するには、自治体や申請状況にもよりますが、一般的に1〜2ヶ月程度の期間が必要です。以下のステップで準備を進める必要があります。
1.福祉窓口で相談する
2.障害児支援利用計画案を作成する
3.申請後に障害児通所受給者証の交付を受ける
4.放課後等デイサービスと契約する
5.個別支援計画書を確認する
6.利用開始
それぞれの手順を解説します。
1.福祉窓口で相談する
放課後等デイサービスの利用を検討している方は、まずお住まいの市区町村に設置された窓口で相談してみましょう。放課後等デイサービスに関する基本的な情報や利用の流れ、申請に必要な手続きなどについて詳しく教えてもらえます。
窓口に訪れる際は、以下の持ち物を持参しておくとよいでしょう。
- 子どもの状況が分かるもの(母子手帳、療育手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、医師の診断書、発達に関する相談記録など)
- 保護者の本人確認書類
子どもの状況を詳しく伝えることで、放課後等デイサービスが本当に必要か、どのような種類のサービスが適切かなど、専門的な視点からのアドバイスが受けられます。困り事や希望する支援内容を具体的に伝えることで、より適切なアドバイスが得られるでしょう。
また、申請の際に必要な書類は自治体によって異なる場合があります。事前に確認しておくことが大切です。
2.障害児支援利用計画案を作成する
障害児支援利用計画案とは、子どもの状況やニーズに基づいた、具体的な支援目標や内容を盛り込んだ計画書のことです。これは、自治体が利用の必要性を判断する上で重要な書類であり、サービス利用の方向性を示します。
一般的には、自治体が指定する障害児相談支援事業所の相談支援専門員が、子どもやご家族との面談を通して作成を支援します。保護者が主体となり、通所支援事業所などの協力を得ながら作成することも可能です。
障害児支援利用計画に基づいて障害児通所受給者証が交付されるため、気になる点や要望があれば遠慮なく伝えるようにしましょう。
3.申請後に障害児通所受給者証の交付を受ける
障害児支援利用計画案の提出後、自治体による審査が実施されます。審査の結果、放課後等デイサービスの利用が認められると、障害児通所受給者証が交付される流れです。
この受給者証には、利用できるサービスの種類や支給量(月ごとの利用日数や時間など)や、自己負担上限額などが記載されています。
受給者証がないと、原則として放課後等デイサービスを利用できません。受給者証は、放課後等デイサービスとの契約手続きや利用開始の際に必要となるため、大切に保管しましょう。受給者証が手元に届くまでには、申請から1〜2週間程度が目安ですが、自治体や申請状況によっても異なります。
4.放課後等デイサービスと契約する
障害児通所受給者証が交付されたら、実際に利用する放課後等デイサービスを選び、契約を結びます。事業所によって、療育プログラムや雰囲気、専門性などが異なるため、子どもの状況やニーズに合った事業所を選びましょう。
契約時には、事業所が定める利用規約や重要事項説明書などの説明を受けて、内容に同意する必要があります。サービス内容や利用時間、送迎の有無、費用などを確認し、疑問点があれば質問しましょう。
契約内容に納得したら、契約書に署名・捺印を行います。契約が完了することで、サービスの利用を開始する準備が整います。
5.個別支援計画書を確認する
放課後等デイサービスとの契約後、子どものニーズに合わせた個別支援計画書が作成されます。個別支援計画書とは、現状の課題や発達段階、興味関心などを踏まえ、どんな目標を設定し、どのような支援を提供していくかを具体的に示した計画書です。ご家庭と事業所が連携して支援を進めていくための重要な指針になります。
事業所から個別支援計画書の案が提示されたら、必ず内容をよく確認しましょう。目標設定や支援内容について、ご自身の希望や気になる点を伝え、事業所と十分に話し合うことが大切です。
6.利用開始
個別支援計画に基づき、放課後等デイサービスの利用を開始します。子どもの様子や気になることがあれば、事業所のスタッフとコミュニケーションを取りましょう。
また、個別支援計画書は定期的に見直しが行われます。その際には、より適切な支援となるように、子どもの成長や変化などを踏まえて、意見などを伝えることが大切です。
最初は慣れない面があるかもしれませんが、焦らずに事業所のスタッフとの信頼関係を築き、連携を取りながら子どもの成長をサポートしていきましょう。
なお、各自治体や事業所によって手続きや流れが異なる場合があるため、必ず関係機関に確認するようにしてください。
放課後等デイサービスの利用料金

放課後等デイサービスの利用料金は、9割を国や自治体が負担し、残りの1割を利用者が負担します。月々の負担金額には上限額が設定されており、所得に応じて適用される額は以下のとおりです。
|
世帯所得ごとの上限額 |
|
|
生活保護世帯・市民税非課税世帯 |
0円 |
|
市民税課税世帯 |
4,600円 |
|
年収約920万円以上の世帯 |
37,200円 |
年収920万円以下の市民税課税世帯で、1回の利用料が1,000円、月に5回利用した場合、本来であれば5,000円の負担金額になります。しかし上限額が適用されるため、月額料金は4,600円です。生活保護受給者や非課税世帯は、利用回数に関わらず、自己負担額は0円になります。
また、利用する事業所によってはおやつ代や活動費が別途必要です。費用の詳細については、事業所に確認を取りましょう。
放課後等デイサービスに関するよくある質問
放課後等デイサービスに関する、以下のよくある質問について回答しました。
- 放課後等デイサービスと学童の違いは?
- 放課後等デイサービスと児童発達支援の違いは?
- 放課後等デイサービスに通うとどんなメリットがあるの?
- 放課後等デイサービスはいつから始めたらいい?
放課後等デイサービスと学童の違いは?
放課後等デイサービスと学童保育(放課後児童クラブ)は、どちらも放課後の子どもたちの居場所を提供する点で共通しています。しかし、対象となる子どもや提供される支援内容に違いがあります。それぞれの対象者は、以下のとおりです。
|
放課後等デイサービスの対象者 |
学童保育の対象者 |
|
・原則として6歳から18歳までの就学して |
・小学生に就学している児童(共働き家庭 やひとり親家庭などの児童が中心。特別な 支援の必要性は問わない) |
放課後等デイサービスでは個々の子どもの状況に応じた発達支援を行うのに対し、学童保育では、児童の健全な育成を図ることを目的に遊びや生活の場を提供します。学童保育の支援員は、子どもの遊びや安全管理を中心とした役割を担っていますが、特別な支援は別途相談になることがあります。
放課後等デイサービスと児童発達支援の違いは?
放課後等デイサービスと児童発達支援は、どちらも児童福祉法に基づく障害児通所支援事業ですが、対象年齢におもな違いがあります。
児童発達支援は、未就学の0歳〜6歳までが対象になる療育サービスです。
関連記事:放課後等 デイサービスの選び方|気をつけることや見学ポイントとは
放課後等デイサービスに通うとどんなメリットがあるの?
放課後等デイサービスでは、子ども一人ひとりの発達段階や特性、興味関心に合わせて、個別の支援計画が作成されます。これにより集団の中では難しいきめ細やかな支援を受けることが可能です。
事業所によっては、言葉の発達がゆっくりな子どもに言語聴覚士による訓練が、運動が苦手な子どもには理学療法士や作業療法士によるサポートが受けられる場合もあります。
また、異なる年齢や特性を持つお友達との関わりを通して、コミュニケーション能力や協調性などを学び、社会性を身につける機会にもなるでしょう。
送迎サービスがある事業所もあり、保護者の方は子どもが通所している間、休息時間や自分の時間を持つことで、心身の負担を軽減できるメリットもあります。
放課後等デイサービスはいつから始めたらいい?
放課後等デイサービスの利用開始時期に明確な決まりはありません。利用開始時期は、子どもの発達段階や特性、家庭の状況などを総合的に考慮して判断することが重要です。
少しでも気になることがあれば、地域の福祉窓口や相談支援事業所に相談することをおすすめします。
まとめ:放課後等デイサービスは安心できる居場所と発達支援を提供する場
放課後等デイサービスは、子どもたちの発達を個別にサポートし、社会参加や自立を促進するための福祉サービスです。
個別支援計画に基づいて、多様なプログラムや個別対応を提供します。子どもの成長や発達をうながす、きめ細やかな支援が特徴です。利用を検討されている方は、ぜひ一度お住まいの福祉窓口に相談してみてはいかがでしょうか。
お子様の発達支援に関心のある福岡の保護者の方は、ぜひ「ちゃれんじくらぶ」をご検討ください。子どもの自信や自立心を育てる活動を行い、一人ひとりの個性やペースに合わせた丁寧なサポートを提供します。
この記事の監修者
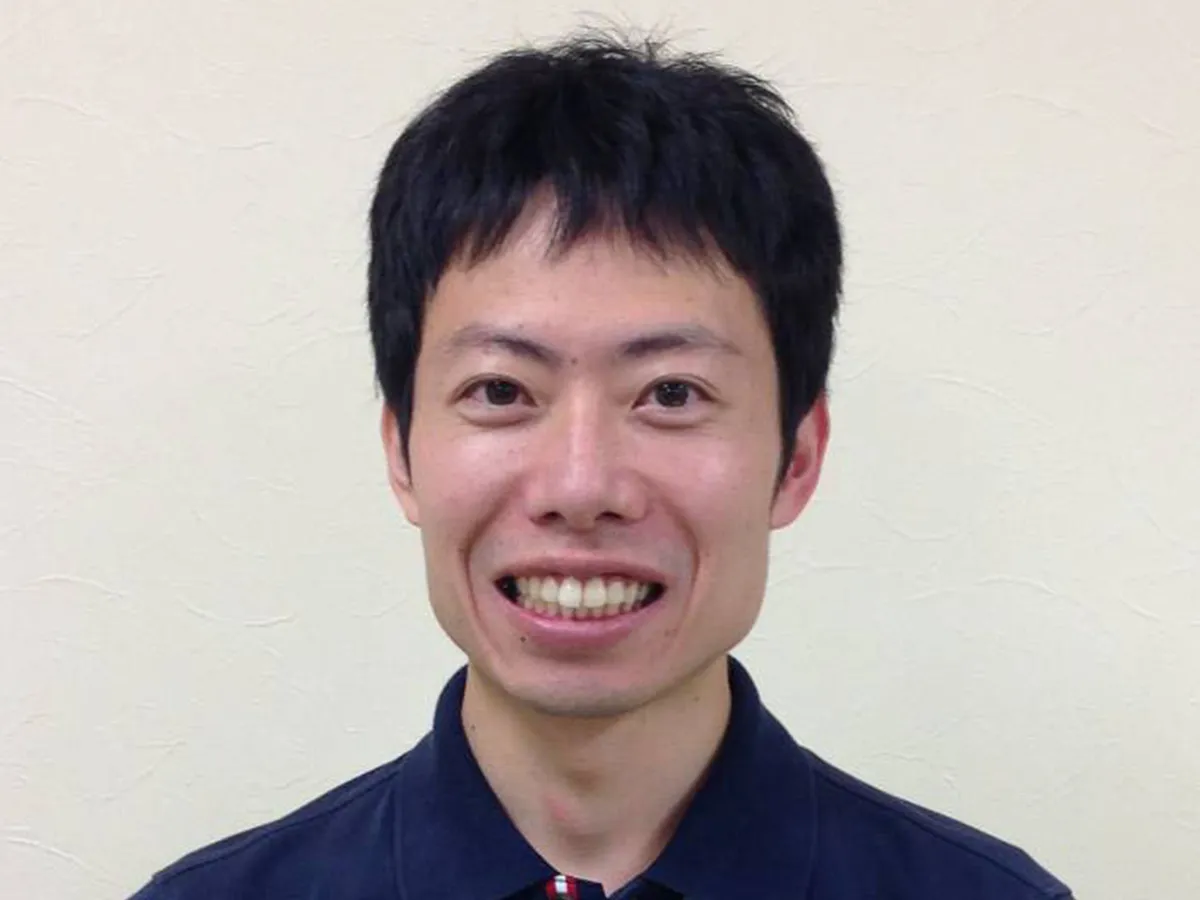
《略歴》
理学療法士免許取得後、医療・介護分野にて回復期や慢性期、通所リハなど多様な現場経験を経て、リハビリ型デイサービスや訪問看護、児童を含む福祉施設の立ち上げおよび運営サポートに従事。
現在は業界歴17年の実績を活かし、放課後等デイサービス「ちゃれんじくらぶ」の運営をサポートしている。
《役職》
三州資材工業株式会社 統括部 総合福祉責任者
株式会社IQOL 取締役
《保有資格》
理学療法士、介護支援専門員、防火管理責任者、介護労働者雇用管理責任者、食品衛生責任者、強度行動障害支援者











